小学3年生で、関西の母の里から東京に移った。
子ども心に、それまで暮らしていた母の里と東京の風土の違いを感じていた。
一番驚いたのが土の色だった。
母の里のあたりは土が砂地に近くサラサラしていて、ベージュ色だった。
一方、東京の土の色は真っ黒なのだ。
後々、学校で関東ローム層というものを習い、それで黒いんだなと納得した。
もう一つ感じていたのは、食文化の違いだ。
たとえば、関西にいるとき「おでん」というものは噂に聞いていたものの、どのようなものか知らなかった。
祖母に聞くと、「関東炊きやね」と言っていた。
祖母の口ぶりからは、あれは関東の物、と受け取れた。
今ネットで調べてみると、そうとも限らないようだが、
少なくとも当時の関西で家庭料理として食べられることは、ほとんどなかったと思う。
また、子どものときから酒のつまみ風のものが好きだった私は、「浜納豆」が大好きだった。

東京に来て、友だちに「浜納豆って知ってる?」と聞くと、
「知らない」と言う。
そのころ東京には、普通の納豆と甘納豆しかなかったようだ。
「鹿のうんこに似てるの」と言うと
「いやだ~汚い」と言われた。
おいしいのになあ。
浜納豆は、もともと三河のものらしい。
ところで、当時同じクラスに、坊主頭の男の子がいた。
体が小さくて、ちょっと味噌っかす的な存在だった。
私の前の席に座っていた。
ある日その子が、
「おめえ、ナルトって食ったことあっか? うっめえぞ」
と、わざわざ後ろを振り向いて言った。
「ナルト? 知らない」と答えた。
「きのう父ちゃんが建前で弁当もらって来て、そん中に入ってたんだけど、うまかったー」と。
彼のお父さんは大工さんの棟梁で、ときどき建前(棟上げ)があると、お土産を持って帰ってくるらしかった。

ナルト……。
どんなものなんだろう?
食べてみたいと切に思った。
家に帰って母に「ナルトってなに?」と聞くと、「かまぼこじゃない?」と言う。
「かまぼこじゃないでしょ? もっと、すごくおいしいものだよ」と言うと、
「じゃ、知らない」と言われた。
それから月日が経ち、なると(鳴門巻き)というのは、おかめうどんなどに入っている紅白の渦巻きのかまぼこだという事実を知った。
ちょっとがっかりだった。
「これか」と。
やがて中学生になり、夕方、玄関の外に出ていると新聞配達の人がやってきた。
肩からたすき掛けにした袋に、新聞をいっぱい入れて走ってきた。
(当時の新聞少年は、たいていこのスタイルで新聞を配った)
あれ? 見たことがある。
あの「ナルトの君」だ!
笑いかけると、ちょっと照れくさそうに笑って返してくれた。
彼、がんばってるんだ……
味噌っかすだった彼が大きく見え、尊敬の念が湧いた。
今頃どうしているだろう、あの「ナルトの君」
お父さんの跡を継いで、棟梁になったのかなあ……。
ヤマヤ醤油 浜納豆 https://ymy.co.jp/hamanatto.php
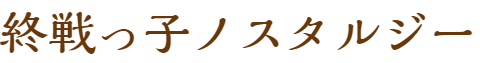




コメント