小学生の英語体験
小学校2年生だったと思うが、母が友人から
「自宅に先生を呼んで子どもたちに英語を教えることになったから、お宅のお子さんもどう?」
と誘われたということで、私と妹はそのお宅に週に一度、通うことになった。
先生というのは大学の英文科を出たての若いお姉さんだった。
挨拶のしかたとか、
「My name is……」という言い方とか、動物の名前や身の回りの物の言い方、
「Pussy cat, Pussy cat」や「London Bridge Is Falling Down」 などの歌を教わり、
とても楽しかった。
饅頭は英語で?
そんなある日、当時大学生だった母の弟が、「まんじゅうは英語でなんちゅうか知っとるか? 」と言ってきた。
「知らない」
「オストアンデルや」と言って嬉しそうに笑った。
「えっ? オストアンデル? 」
すぐには分からなかったが、やがてわかり、ちょっとしたことでも笑い転げる私は大いに喜んだ。
続けて「じゃあ水道は? 」
「?」
「ヒネルトジャー」
月桂冠を望マンデー
そしてこんなことも教えてくれた。
月桂冠を望マンデー
火に水かけてチューズデー
水田に苗をウエンズデー
木刀腰にサースデー
金ぱつ料理はフライデー
お土産持ってごぶサタデー
なぜ日曜日はないの?
なぜ土曜日が「おみやげ」なの?
という疑問があったが、なるほど土産(みやげ)と書くからだということは、かなり後になって分かった。
中学に入り、英語は自分の得意科目だと思い込んでいたが、高校生になり分詞構文などやたら難しくなって、さっぱりわからなくなってしまった。
私はいつも、一度わからなくなると、めんどくさくなってそれ以上わかろうとしない。
英語にもそれが出たようだ。
(追記)当時「金ぱつ料理」の意味が分からなくて、母に聞いたことがある。
「特別に奮発した料理のこと」と教えてくれたが、今回調べてみたら、辞書にもネット上にもなかった。
どうやら正式な言葉ではなさそうだ。
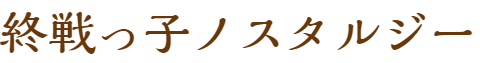




コメント