「菩提樹」の感動も冷めやらぬまま季節は春の息吹を感じさせる頃となり、
担任の先生たちは、卒業式に向けての準備に余念がなかった。
よびかけ
今は卒業式のやり方にもいろいろと趣向を凝らしたりして型にはまらない個性的な式が増えているようだが、
当時は、卒業生の代表が答辞を読むといった儀式的な色彩が強かったと思う。
私たちの担任団は「表現」ということに熱心だったので、いわゆる答辞は「よびかけ」という形で行うことになった。
「よびかけ」というのは今もあるかもしれないが、
全員が舞台に上がり長い散文詩のようなものを全員で発声するコーラス部分と、
一人が発声するソロ部分とで構成されている。
要は集団で行う詩の朗読のようなものだ。
そのころ学芸会の演目には、必ずこの「よびかけ」が入っていた。
わたしはこの「よびかけ」なるものがあまり好きではなかったが、やる以上は一所懸命やろうと思った。
まず先生方はみんなに小学校生活の思い出を作文に書かせ、
その中からこれはと思う部分をピックアップしてつなげ、長い詩のような形にする作業を行った。
私のクラスの担任の先生は若いころ小説家志望だったとのことで、このような作業はむしろ楽しかったかもしれない。
そして出来上がったものをみんなに覚えさせ、何回も練習した。
エルガー「威風堂々」
担任団は素晴らしい式にしようと演出にこだわり、卒業生の入場曲に エルガーの「威風堂々」を選んだ。
いまでこそ あちこちで始終聞かれる曲となっているが、当時はそれほどポピュラーではなかった。
私はこの「威風堂々」がとても気に入った。
先生は、曲のどの部分になったら入場していくかにこだわっていて、たくさん練習させられた。
卒業式当日
いよいよ卒業式当日となった。
私たちは大勢の参列者が見守る中、マーガレットの花を胸につけ「威風堂々」に乗り、厳かに入場していった。

そして答辞の「よびかけ」が始まった。
私はその口火を切る役だった。
BGMが流れ始める。
先生が舞台の袖にかくれながら「ここだぞ!」と言う風に全身で合図するのが見えた。
それっ、とばかりに斜め上を指さして「3月の空!」と発声した。
その後に、みんなのコーラスが続く。
しばらくして、私のソロの番になった。
内容は臨海学校の思い出だった。
間違えずに言えてホッとした。
コーラスとソロの掛け合いが続き「よびかけ」は無事終了。
卒業式も滞りなく終わった。
思えば太平洋戦争が激化した戦争末期、
防空壕で生まれた子もいる
生まれてもすぐ死んでしまった子もいる
そもそも生まれてくることができなかった子もいる。
そのような中に生まれてきて、様々な辛苦をもって大切に育てられた私たち。
参列していた人々は、よくここまで無事に育ってくれたと感慨もひとしおだったに違いない。
散りかけた桜の木の下で、私は長かった小学校生活を終えた。
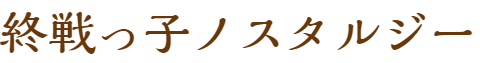
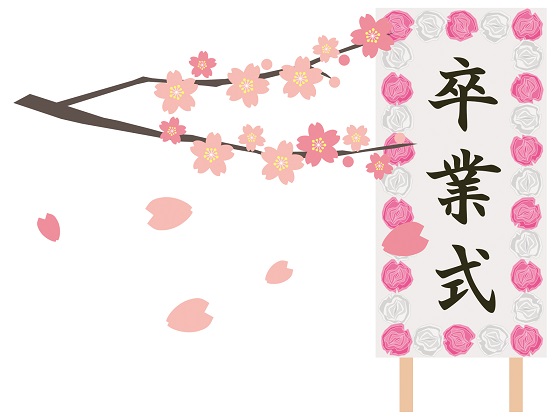






コメント