当時お米には、いろいろな種類があった。
といっても「コシヒカリ」とか「ひとめぼれ」とかの種類ではない。
配給米、ヤミ米、内地米、外米などの種類である。
各家庭には米穀通帳というものがあり、預金通帳のような形をしていた。
それが何のために必要なのかはよく知らなかったが、
おそらく食糧難の時代に、お米を国民にできるだけ平等に分ける必要があったのだろう。
政府が管理する配給米だけでなく、民間ではヤミ米というものも流通していたらしい。
母が「じゃあ、米穀通帳を持っていけばいいんですね」などと確認しているのを聞いたことがある。
お米関係だけでなく、身分証明書のような役割もあったのではないかと思う。
自分の家がいつ配給米を食べていて、いつから自主流通米になったのか、などはよくわからないが、
父が「この飯はまずいな。外米じゃないのか?」などと言っていたのを思い出す。
外米とは要するに輸入米のようなものだ。
時々 知り合いの家に行くと
そこでお母さんやおばあさんが新聞紙などの上にお米を広げて、石とか汚いお米をより分けていたのを覚えている。

米離れということをちょくちょく聞くが、米ほどありがたい食料はないのではないだろうか。
いつか、アフリカの飢餓の子どもたちのことをテレビで見たときのこと。
そこで救援活動をしている方が、
「みな栄養失調でガリガリに痩せて、皮膚病になっていたり、おなかが悪くなったりしているが、
おもゆを飲ませると、どんどん良くなるんですよね」
と言っていたのを思い出す。
米は大切だ。

非常用おかゆ10袋セット
そのまま食べられ、スプーン付きで便利

迫る食料危機! 私たちの食と農を守るためにできること㊤ 東京大学大学院教授・鈴木宣弘 | 長周新聞
世界情勢の複合的な要因と食料自給率の低迷による食料危機が、日本でも現実問題として迫っている。そのなかで現在、全国各地で精力的に講演活動をおこなっている東京大学大学院農学生命科学研究科教授の鈴木宣弘氏が10月22日、埼玉県狭山市で「迫る食料危...
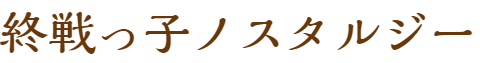




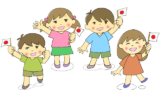

コメント