父の会社も軌道に乗り始め、私たちは東京の父のもとに帰ることになった。
小学2年と3年の間の春休みのことだ。
東京駅に着くと、父と、母の従姉妹が迎えに来ていた。
当面は父の実家で暮らすことになっていた。
その家に着くと、父方の祖母が玄関に迎えに出て私に何か話しかけた。
どう答えたかは覚えていないが、祖母は「ずいぶんこまっしゃくれた子だねえ」と言った。
「こまっしゃくれた」という言葉は初めて聞いたので意味はよくわからなかったが、子ども心に「子どもらしくない、かわいくない」というニュアンスを感じた。
この父の実家は子どもから見ると奇妙な家庭だった。
祖母は家の裏に自分用の小さな家を建て、そこに住んでいた。
今で言うなら家庭内別居だ。祖父の食事を作るときだけ母屋に来ていた。
祖父は終戦まで外務省の役人であったので、あちこちの海外生活が長く英語が堪能であった。
聞いているラジオは常にFENだった。
アナウンサーが区切り区切りで言う「Far East Network」が、「フォーリースネッワー」と聞こえた。
これが一日中聞こえていたように思う。
祖父は私と妹に、朝、顔を合わせたら「Good Morning」、夜寝るときは「Good Night」と挨拶するよう強要した。
初めはとても嫌だったが、じきに慣れてしまった。
祖父の書斎には、剥製のオウムや珊瑚の置物、東南アジアの調度品のようなものなどが所狭しと置いてあった。
また、祖父の寝室の欄間のところに水牛の角が飾ってあり、祖父が寝るために電気を消すまで、隣の私たちの寝室から欄間の障子を通して見えた。
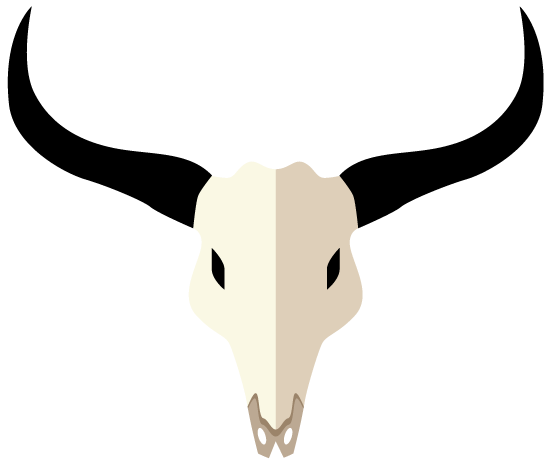
これらさまざまな物は、物珍しくもあり、不気味でもあったが、だんだんそれらに馴染んでいった。
子どもというものは、こんな風に望むと望まざるとにかかわらず、大人の都合によって生活ががらりと変わることを受け入れていくものなのだなあと今思う。
こうして東京の生活が始まった。





コメント