1年生のころは、学校に行くことが楽しかったという覚えがない。
学校が家のすぐ前だったから、5分前に出れば間に合う。
裏口に座って靴を片一方履いて、しばらくぼんやりしていたことがある。
すると母がやってきて「あら、まだ靴はいているの? スローモーねえ」と言って、どこかに行ってしまった。
すると気持ちが切り替わって、もう一方の靴を履き出かけていく、といったぐあいだった。
あるとき自分で風邪をひいたと申告し、自主的に学校を休んだ。
ずる休みである。
風邪を引いた証拠として、ずっとパジャマで過ごした。
母は仮病だと気づいていたと思うが、何も言わなかった。
母の弟が「学校さぼっとんのか?」と言ったが、
「風邪ひいてるんだもん」と返した。
たしか1週間ぐらい休んで、また自分から行き始めたと記憶している。
そのときは自分のことがあまりわからなかったが今考えてみると、おそらく学校に行くことが負担だったのだろう。
要は休んで正解なのだ。
学校へ行く時間に、ラジオで何かの番組のテーマとして ヨハン・シュトラウスの「アンネン・ポルカ」が鳴っていた。
これが鳴り始めると、学校へ行かなければならない。
あれから 70年弱が経った今でも、この曲を聴くと、
あの給食のムッとするにおい、
ガヤガヤした大勢の人の中に入っていく圧迫感、
なんだかよくわからないことがたくさんある漠然とした不安感のようなものが入り混じった不穏な感覚が、胸のあたりにざわざわする。
ヨハン・シュトラウスの曲だから、そんな記憶と結びついていなければ、きっとかわいい曲のはずなのに、どうしてもこれを聞くと胸がざわざわして不穏な感じになる。
記憶とは不思議なものである。

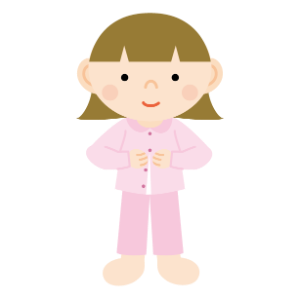

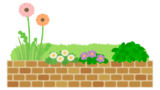

コメント