続きです。

アルブミンが 3.5 を切るとお迎えが来ます
100種類以上ある血液中のたんぱくのうち約60~70%を占めているのがアルブミン(ALB)。
血液中の水分を一定に保つ働きや、栄養・代謝物質を運搬する役割を持っている。
アルブミンはおもに肝臓でつくられ、腎臓でろ過されずに血液中に存在しているため、アルブミン値の異常は、肝臓や腎臓の機能障害の指標となる。
基準値 3.9 g/dL以上(日本人間ドック・予防医療学会)
●基準値より低い場合に疑われる病気など
肝硬変などの肝機能障害、ネフローゼ症候群、栄養不良など
参考「みんなの家庭の医学 WEB版」
https://kateinoigaku.jp/knowledge/detail/311
結論として私の体は、食べたものをエネルギーに変えるシステムがちゃんと働いておらず、自分の肉体(筋肉、腸粘膜など)を餌として食い、それをエネルギーに変えてしまっているという恐ろしいことだった。

心臓の主治医(心臓血管外科や循環器の専門医)曰く……
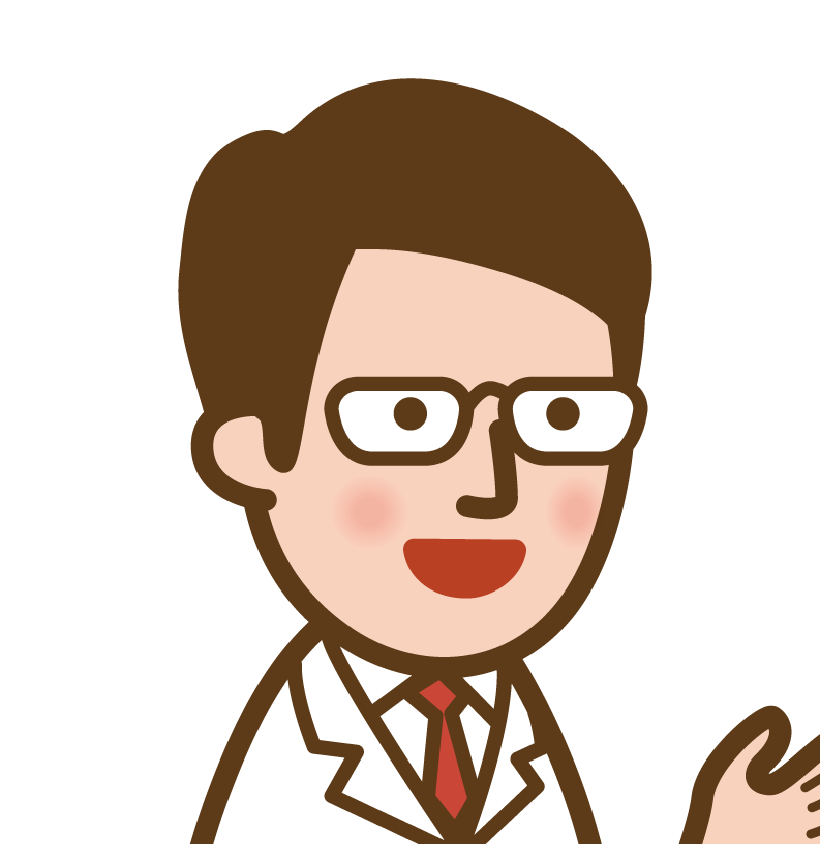
あなたは筋肉がないから体重が増えない、運動しないと筋肉が増えない
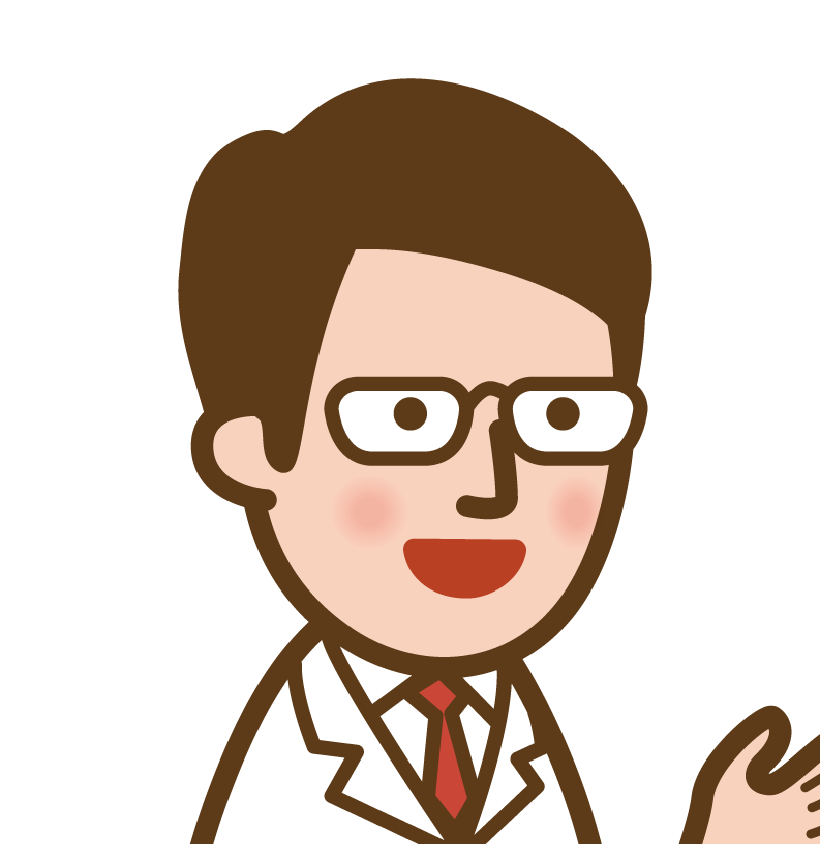
35㎏? それはやせすぎですよ
という、私には解決にならない回答だった。
そもそも癌で 50年近く前に胃の2/3を切除しているので、容易に食後高血糖になり数時間後に低血糖になる。
ダンピング症候群
https://www.ringe.jp/civic/20200302/p13
日本臨床外科学会
(13) 退院後に起こる問題と対処法 胃切除後症候群とは
低血糖時には、肝臓でアミノ酸を分解して糖に作り替えて血糖値を維持しようとする(糖新生)。この過程でALT(ビタミンB6が必要な酵素)を使う。
私はALTが極端に低く、この過程が亢進していると考えられる。
肝臓で糖に作り替えるとき、もっとも使われやすいタンパク質が筋肉と腸だとのこと。

原因として考えられるのは……
ビタミンDが著しく少ない
亜鉛が少ない
鉄が少ない
ビタミンBが少ない

糖尿科の主治医が検査結果を見るのとは大違いだ……

肝臓よし、腎臓よし、骨よし、カルシウムよし
と花丸をつける、めちゃアバウト。

食事:血糖値のコントロールが大切

糖尿科の主治医は……

万遍なく食べてください。お菓子はダメです。よく噛んで
のみ。実にアバウト。

不足している要素をサプリメントで補います
マルチビタミンとかマルチミネラルとか亜鉛とかビタミンDとかアミノ酸とか消化酵素とか鉄とか。
様々なサプリを購入することとなり、代金はしめて5万円強。
この中には3か月分というものもあり正確に計算すると、ひと月3万円強となった。
このサプリは医療用で、診療を受けているクリニックの「クリニックキー」という暗証番号のようなものを入力しないと注文できない。
この療法をやっているクリニックは、わが県にはなく他県まで赴いた。
交通費もかかるし、自由診療のため検査費や診療費など、やたらとお金がかかることになったが、しばらく続けてみようかと思った。
それは、この女医さんの説明に納得がいったから。
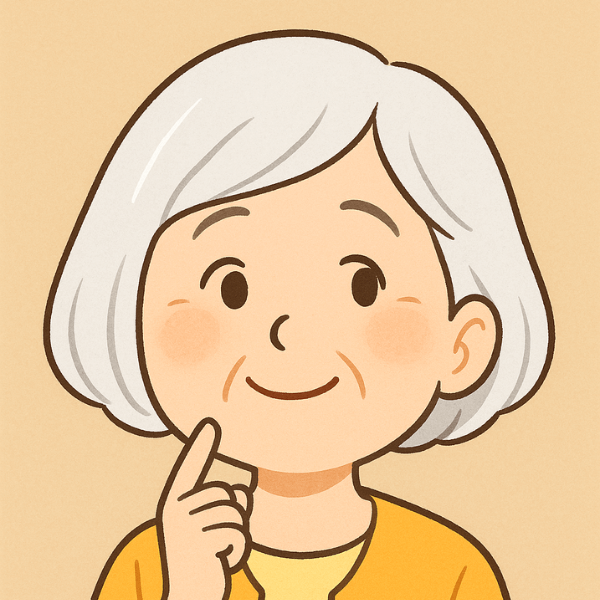
糖尿科の主治医より、ずっと具体的に食事指導をしてくれるし、検査も詳しくて分析もきちんとしてくれる。
ちなみに、このクリニックのトイレは超綺麗、ここでやってもいいの? と恐縮するくらい。
スタッフもとても親切、丁寧で感じよい。
さて1年後どうなったかは、また後程ご報告いたします。
その前に、この栄養療法にたどり着くまでの経緯を「コロナその後」としてまとめましたので、次回はそれをご紹介します。
【肝臓の働き】糖代謝・タンパク質代謝・脂質代謝
YouTube チャンネル ゴロー/イラストで学ぶ体の仕組み
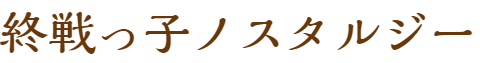
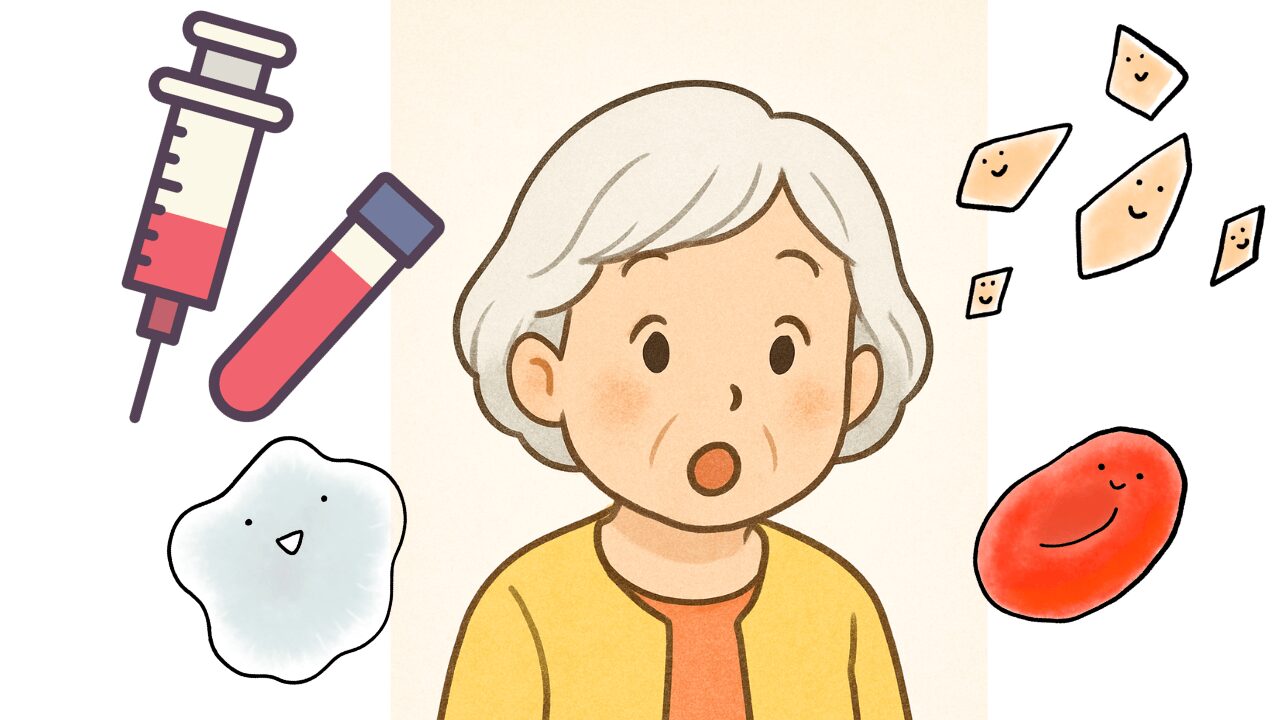




コメント
オーソモレキュラーのことを教えて下さってありがとうございます。
興味があったので、ネットで調べてみました。
身体は食べた物でできているのはわかるけれど、人によって設計図は違うよな~…と、思っていたので、とてもしっくりきました。
続きを楽しみにしています。
ogu-mamaさま
ご丁寧に読んでいただいて、ありがとうございます😊
人の体はまことに精密にできており、こうやって何とか生きていることが奇跡のような気がします。
この療法を受けて1年ほど経過したときのことをまたお伝えしますが、次回はコロナの後遺症に関して少し述べようと思っています。
調べてみたら、母の通っている病院もオーソモレキュラー療法の先生がいらしゃるようです。
専門は産婦人科の担当医なのですが…(笑)
オーソモレキュラーは、それが専門というより他に専門があってこの療法を勉強される医師が多いようです。
田舎と違って大都市にはこの療法を実施しているところがたくさんあると思います。
次回は「オーソモレキュラー1年後」についてお伝えするつもりです😊