1950年代になっても、まだ水道が引かれていない地域がけっこうあった。注1
うちもそうだった。
井戸水を電気ポンプで汲み上げて使っていた。
井戸水は、夏は冷たく冬は温かい。
ビールや(そのころは瓶ビールが普通だった)すいかを、裏の流しで井戸水を流しっぱなしにして冷やしたものだ。
冷蔵庫は氷で冷やす仕組みで、扉が分厚く、容量が小さく、すいかを入れる隙間がなかったように覚えている。
当時は氷屋さんが氷を配達した。
氷をのこぎりで切る音が、とても涼やかだった。
氷屋さんは、冬になると炭屋さんになった。
いわゆる三種の神器と呼ばれた電気製品のうち、洗濯機は母の訴えでかなり早くから導入されたが、テレビと冷蔵庫は、私が中学生になってからである。注2
そのころの洗濯機はと言うと、「しぼりき」というものがついており、洗い終わった洗濯物を、ローラーの間に挟んでハンドルをぐるぐる回して絞るというものであった。
とはいえ、タライと洗濯板で洗濯する重労働から解放されて、母もずいぶん楽になったはずだ。

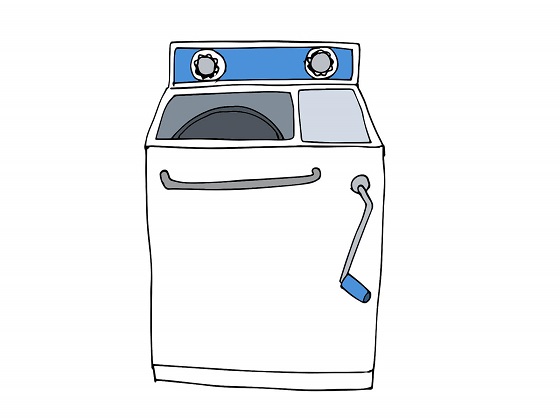
朝は、牛乳屋さんが自転車で配達する音で目が覚めたものだ。
家々の裏口辺りに牛乳箱が設置されており、そこに配達される。
空の瓶は持って行ってくれる。
考えてみると合理的だ。
電気冷蔵庫が来てからは、その牛乳瓶が1リットル入りの大きな瓶に変わった。
今では1リットル入りのパックは普通だが、そのころはとても大きな瓶に見えた。
アメリカの家庭みたいだなあと思った。
また、母のいわゆるママ友で、母よりかなり年上だった方に「電気掃除機、あれはいいよ」と勧められ、さっそくそれも導入された。
テレビについては、また別の機会に書こうと思うが、こんな風にして家庭電化が始まったのである。
注1 厚生労働省「水道普及率の推移(平成30年度)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000624219.pdf
厚生労働省「水道の基本統計」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/database/kihon/index.html
注2 帝国書院「耐久消費財の世帯普及率の変化」
https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/history_civics/index13.html
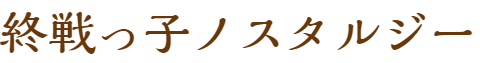



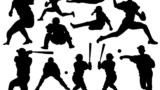
コメント